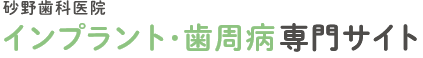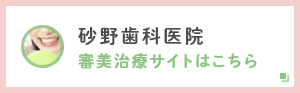歯周病とは
歯周病とは

歯周病の原因
歯垢(プラーク)
細菌がいること自体には問題はありませんが、何らかの原因によってこの細菌が過度に増加したり、細菌に糖分を含んだ食べかすが付着する事により『歯垢(プラーク)=細菌の塊』が、歯だけでなく歯の周りに強力に付着します。
この歯垢が歯肉(歯ぐき)の炎症を引き起こし、歯槽骨、歯根膜を溶かしていく、歯周病の原因となるのです。
歯石
喫煙
しかし、たばこに含まれるニコチンは、血液の流れを悪くし、身体の自然治癒力を下げるといわれていますので、歯周病になりやすく、喫煙し続けていると歯周病も治りにくくなってしまいます。
またタバコにはニコチン以外にも多くの有害物質が含まれておりますので、喫煙をやめない限り、歯周病は治らないと言っても過言ではありません。
歯並びの悪さ
歯並びが良い人は神経質に歯磨きをしなくても磨き残しが少なく、付着した歯垢(プラーク)も除去できている事が多いのですが、歯並びが悪い人、特に歯と歯が重なり合っているような場合、どんなに丁寧に歯磨きをしても重なり合っている部分はどうしても磨き残しが多くなってしまうためも、歯垢(プラーク)も付着しやすく、付着した歯垢(プラーク)を除去しにくくなりますので、歯周病になりやすくなります。
詰め物、被せ物の不適合
歯周病の進行と症状
歯周病の初期

症状
- 歯磨きをすると出血することがある。
- 歯磨きを1回でも忘れると、歯が疼いたり、歯ぐきが腫れぼったく感じることがある。
内部の状態
歯の周囲の歯ぐきに隠れてしまう場所に歯石などが付着し始めています。
歯を固定している骨のダメージはほとんどなく、歯石を取り歯磨きをしっかり行なえば改善できます。
歯周病の中期
症状
- 水がしみるようになり、歯磨きすると歯ぐきから出血する。
- 歯ぐきがときどき腫れたり、治ったりを繰り返す。
- 歯ぐきを押すと膿が出る。歯ぐきから臭いがする。初期の段階から数年経過すると見られることが多い。
内部の状態
初期よりも歯の周囲の深い場所に、内部に歯石などが付着している。
歯にぐらつきは無いものの、周囲の骨も溶け始めている。
歯と歯ぐきの溝が深くなり歯磨きだけでは、汚れが取れないため、進行が止まりにくい。
歯周病の末期
症状
- 歯を噛み合わせるだけでぐらつく。
- 歯の周囲を指で押すと白い膿が歯の周囲からにじみ出てくる。
- 痛みが出ないこともある。歯磨きの際、毎回のように出血する。
内部の状態
歯の根の先の奥深い部分まで、歯石の付着している。歯ぐきが歯を固定せず剥がれている状態。歯を支える骨も溶けてしまっている。
歯周治療の流れ
歯周病の治療は、進行時期によって主に3つの方法が選択されます。
1 スケーリング(主に初期の歯周病)
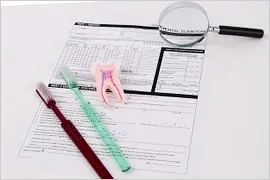
初期の歯周病では、歯石の付着している部分が、歯ぐきの内部のごく浅い部分に付着しているため、超音波スケーラーや、ハンドスケーターなどを利用して、無麻酔で取り除きます。
2スケーリング、ルートプレーニング(初期~中期の歯周病)
スケーリングだけでは、取りきれないような歯ぐきの少し深い位置にある歯石を麻酔を使用してから取り除き、さらに歯石が付いていた根の表面を滑沢な面に仕上げます。
3 フラップ手術(中期~末期の歯周病)
スケーリング、ルートプレニングでは、歯と歯ぐきの隙間に器具を挿入して、歯ぐきの中を、主に手探りで歯石などを取り除きますが、フラップ手術では、麻酔後に歯の周囲の歯ぐきを切開して、歯ぐきの奥の汚れを直視下で取り除きます。
基本的には1→2→3の順に段階的に行われます。歯周病の治療で共通しているのは、歯の表面についている歯石(細菌)を取り除いているということです。
歯周病の原因は様々ですが、治療で特に大切なのは毎日の歯磨きです。特に中期~末期の歯周病の場合、それまでの歯磨きがしっかりしていたとは考えにくいので、歯磨きに対しての考えを根本から変化させるぐらいの気持ちで臨まないと、なかなか歯周病から抜け出せません。